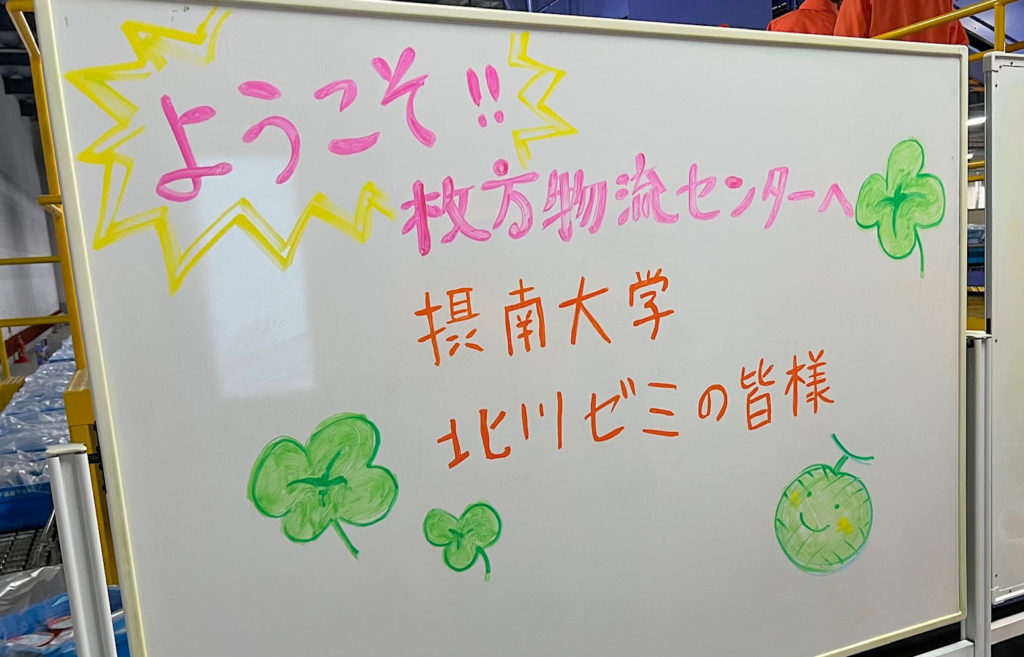食農ビジネス学科食品産業研究室
UPDATE 2025-07-02
2025年6月28日(土)朝、大阪市浪速区にある大阪木津地方卸売市場を、食品産業研究室(山本尚俊教授ゼミ)の3年生10名のうち7名が訪問しました。
大阪木津地方卸売市場(1913~31年の木津難波魚青物市場、~38年の大阪市中央卸売市場木津配給所、~73年の大阪木津卸売市場を経て、以後、現在の名称に)は民設民営の卸売市場で、そのルーツは1710年頃の野立ち売り(いわゆる市)に遡り、また官許の取引の場として正式に認知を得たのは1810年頃と言われます。卸売市場と言えば、大阪市福島区の大阪本場や東京の豊洲市場等をイメージしやすいですが、それら公設卸売市場(中央卸売市場)制度が誕生する遥か昔から人々の食や暮らしを支えてきたのがこれら民設民営の市場です。国の市場・流通政策はじめ移り行く時代の変化とともに、これら民営市場も役割やあり方を少しずつ変えながら現在に至っています。
ゼミ生は、大阪木津卸売市場内の視察だけでなく、当該市場の起源やその後の史的展開、現代の姿を知り、また今なお京阪神近郊産地の生産者や出荷者が選択的に産品を持ち込む“価値実現の場”として、そして大阪近隣の飲食事業者等が仕入に訪れる「なにわの台所」、食の拠点として、重要な役割を担うことを学びました。
当日は、元・大阪木津卸売市場の職員で、現在、(一社)日本食育者協会 事務局としてお勤めの太田雅士さんにご協力いただき、市場内各所の見学から、別室に場所を移しての座学的なレクチャー、討議まで、木津市場や大阪の食について理解を深める学びの機会をご提供いただきました。本見学にご協力いただきました太田さんはじめ仲卸業者の皆様方にこの場をお借りして御礼申し上げます。

食農ビジネス学科食農共生・協同組合研究室
UPDATE 2025-06-24
おおさかパルコープの方々のご協力を得て、宅配事業の拠点である枚方物流センターを訪れました。職員の福利厚生に力を入れ、障がい者も積極的に雇用し、フードバンクとしてこども食堂への供給も行うなど、生協が組合員だけではなく地域のためにさまざまな役割を担っていることを学びました。
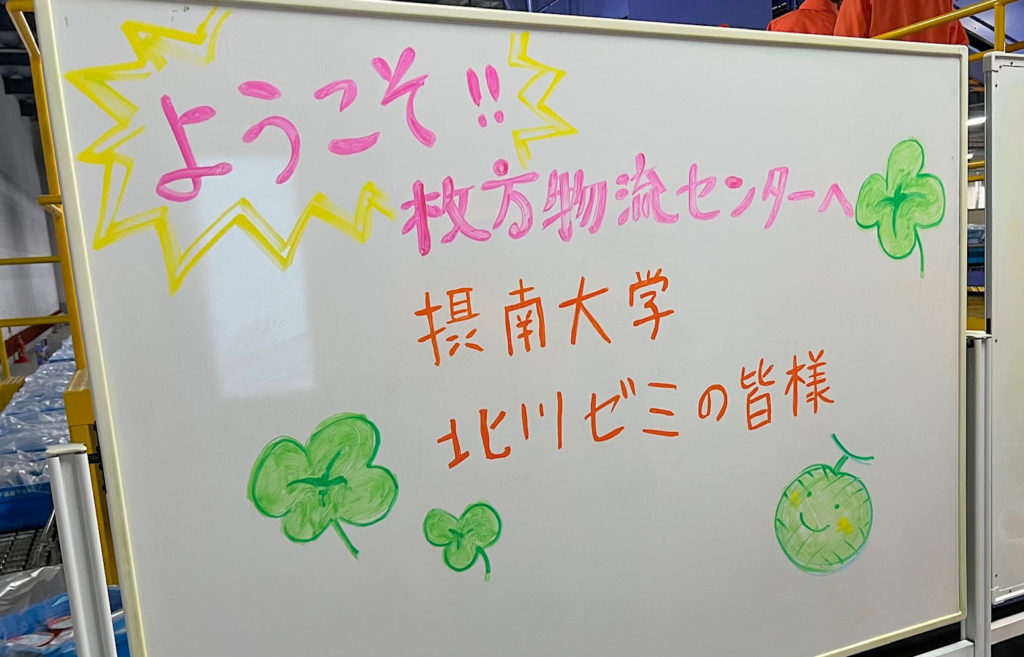

食農ビジネス学科食品産業研究室
UPDATE 2025-06-06
2025年6月3日(火)、京都府長岡京市にあるサントリー<天然水のビール工場>京都を、食品産業研究室(山本尚俊教授ゼミ)と地域マネジメント研究室(浦出俊和教授ゼミ)の3年生17名が見学しました。
飲食料品製造業のなかでもビール産業は大手メーカー数社による寡占構造が際立ちます。その上位メーカーの1社であるサントリーの京都工場を訪問し、ビールの製造や商品化の過程は勿論、同社の沿革や創業者のこだわり等について学びました。
各種機器を備えた巨大な工場は圧巻ですが、そこで量産されるビールは麦やホップなど原材料に拘り、各製造工程には専門の担当者を配置、徹底した品質管理のもとで製造されていました。また、同社のものづくりの源は水として、水にこだわり、「水と生きる」を企業理念に、地下水を育む森づくりにも積極的に取り組まれていることを学びました。CMで良く見聞きする「水と生きる」の意味が非常によく理解できたのではないでしょうか。
この見学に際し、食品産業研究室のゼミ生には一つのお題を出しています。それは、今日、各地で事業化が進むクラフトビール醸造が、寡占構造を特徴に持つビール市場において、大手メーカー品との差別化や競争優位をいかに生み出すことができるのかを考えることです。大手メーカーのビール工場をみてどう感じたかを含め、後日意見を尋ねてみたいと思います。